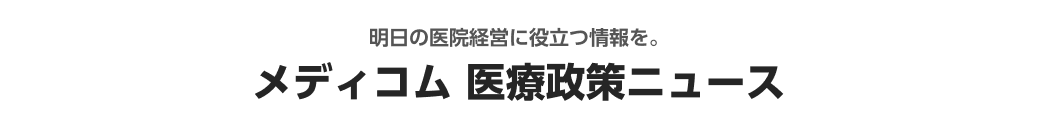
《ここがポイント!》
- 8月21日に行われた「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」では、出産に伴う経済的な負担の軽減策などが議論された。妊娠中の女性や関係者などへのヒアリングが行われ、周産期医療・保険・ケアへの無償化や専門的支援に誘導できる仕組みを整備するなど、費用の負担軽減を求める意見が出た。
- 調査では、「出産育児一時金(42万円)」以下で産めた人はわずか7%にとどまり、「61万円以上」は全体のほぼ半数を占めたと発表。
- また、赤ちゃん本舗が行った調査では、政府が行う支援事業の認知度の低さが明らかとなり、支援事業の「見える化」など利用されやすい環境づくりが重要と指摘された。
~妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第3回 8/21)《厚生労働省》~
出産に伴う経済的な負担の軽減策などを議論する検討会が21日、妊娠中の女性や関係者などへのヒアリングを行い、周産期の医療・保健・ケアを無償化して専門的な支援に誘導できる仕組みを整備するなど、費用の負担軽減を求める意見が出た。
ヒアリングを行ったのは、厚生労働省とこども家庭庁の「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」で、関係者のヒアリングには、「子どもと家族のための緊急提言プロジェクト」の共同代表で医師の佐藤拓代氏などが参加した。
その中で佐藤氏は、2022年に行った出産費用に関するウェブ調査の結果を紹介した。この調査では、18年1月以降に出産した47都道府県の女性1,228人から有効回答があり、出産育児一時金42万円(当時)以下の費用で出産できたのは7.0%にとどまった(資料1-P4参照)(資料1-P5参照)。これに対し、「61万円以上」は全体の47.3%とほぼ半数を占め、それらの83.3%が首都圏(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)の女性だった(資料1-P5参照)(資料1-P6参照)。
佐藤氏は、英仏など欧州7カ国では正常分娩に公的保険が適用され、うち5カ国では自己負担が掛からないとする調査結果も紹介した(資料1-P17参照)。フィンランドでは、無料の妊娠出産育児相談所「ネウボラ」を妊娠中の女性の大半が利用しているといい、佐藤氏は、周産期の医療・保健・ケアを日本でも無償化して、専門的な支援に誘導できる仕組みを整備することを提案した(資料1-P18参照)。
正常分娩に公的医療保険を適用することで医療の標準化につながることなどへの期待も示したが、検討会のメンバーからは「保険適用イコール出費が減るとイメージだけで期待している人が多いのではないか」(中西和代・たまごクラブ前編集長)という意見があった。
検討会は、夏ごろにヒアリングを3回程度行う予定で、今回が2回目。出産に関する支援策などの本格的な議論を秋以降に始め、25年春ごろ取りまとめる。
関係者へのヒアリングでは、妊娠・出産に伴う費用負担の実態を明らかにするため「赤ちゃん本舗」が8月9日-11日、アプリの登録者を対象に行った調査結果の報告もあった。
この調査では妊娠・出産・子育てを経験した女性やパートナーなど7,500人が回答し、国や自治体が行う支援事業の認知度の低さが明らかになった(資料2-P8参照)(資料2-P11参照)。
そのため同社の西峯佳恵氏は、どんなに良いサービスを作っても利用されなければ価値は著しく下がると指摘し、支援のメニューを整理して「見える化」するなど事業を利用しやすい環境作りを求めた(資料2-P13参照)(資料2-P15参照)。
また、妊娠・出産・産後にどんな支援が必要かの質問では、おむつや粉ミルクの購入など産後の費用負担の軽減を求める声が特に多かったといい、西峯氏は出産時以外の支援の必要性も訴えた(資料2-P14参照)(資料2-P15参照)。
(資料公表日 2024-08-21/MC plus Daily)
資料1:「妊娠・出産の無償化」と国際水準の「継続ケア」の実現
資料2:赤ちゃん本舗 ユーザーの声を中心とした報告
※本コンテンツは株式会社日本経営から提供を受けていますが、掲載内容につきましては、メディコムパーク編集部がタイトル・見出し等を一部編集・加工しています。
メディコム 人気の記事
イベント・セミナーEVENT&SEMINAR
お役立ち資料ダウンロード
- クリニック・
病院 - 薬局
-
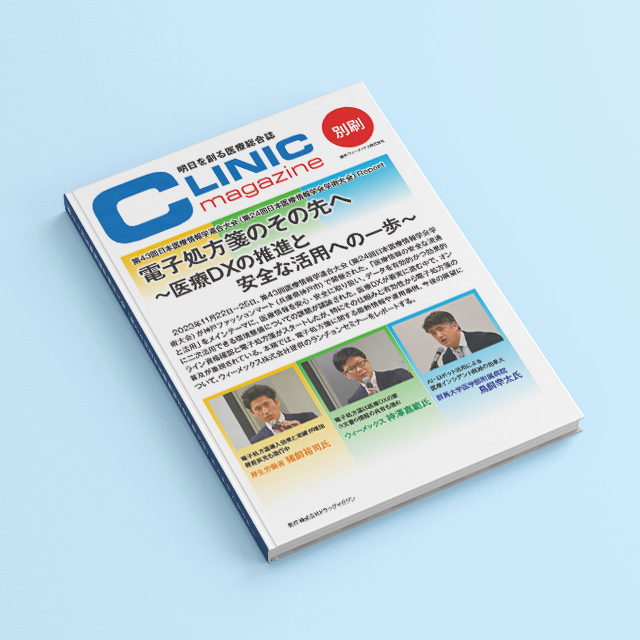
医療政策(医科) 医師 事務長
第43回医療情報学連合大会 ランチョンセミナー
-
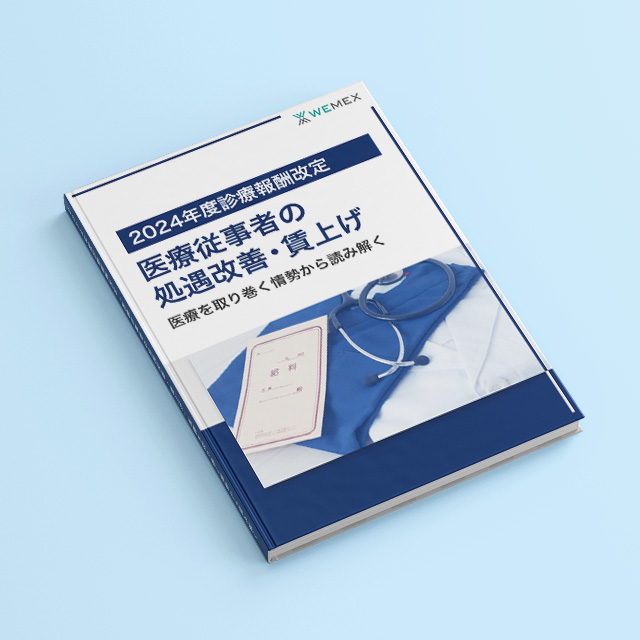
医療政策(医科) 医師 事務長
2024年度診療報酬改定「医療従事者の処遇改善・賃上げ」
-

医療政策(医科) 医師 事務長
第27回日本医療情報学会春季学術大会 ランチョンセミナー
-

医療政策(医科) 医師 事務長
電子処方箋の活用でタスク・シフトが実現できるのか?
-
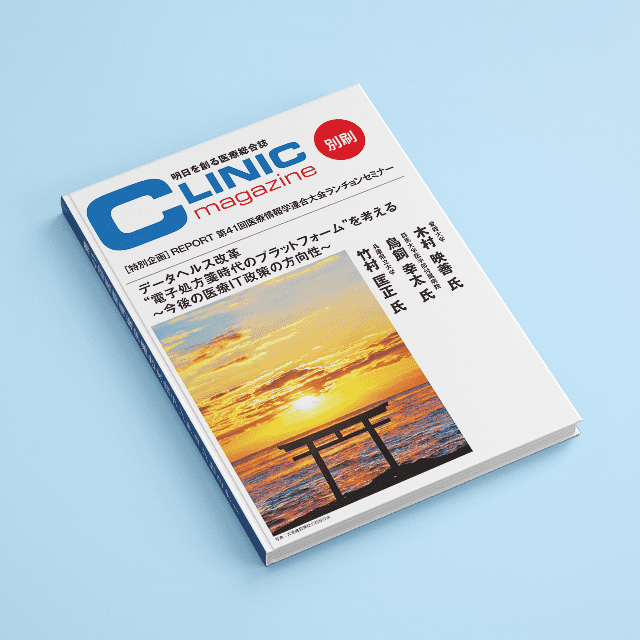
医療政策(医科) 医師 事務長
第41回医療情報学連合大会ランチョンセミナー
-

医療政策(医科) 医師 事務長
オンライン資格確認スタート/アフターコロナを見据える
-

医療政策(医科) 医師 事務長
地域連携はオンライン診療の起爆剤となるか?
-
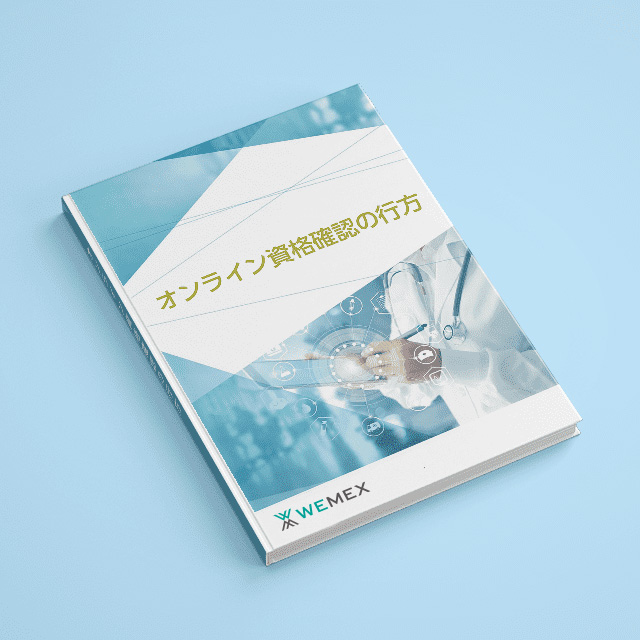
医療政策(医科) 医療政策(調剤) 医師 薬局経営者
オンライン資格確認の行方






