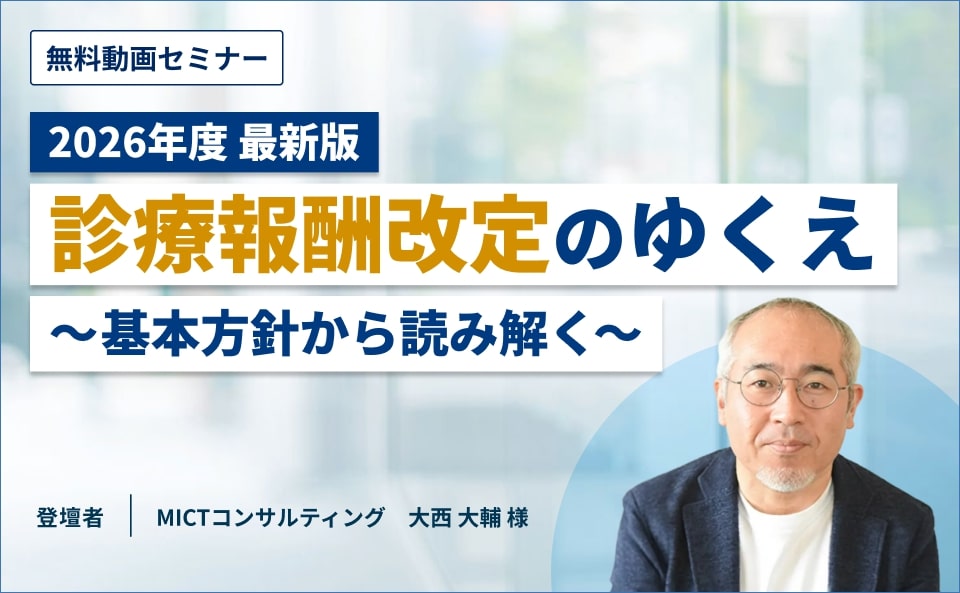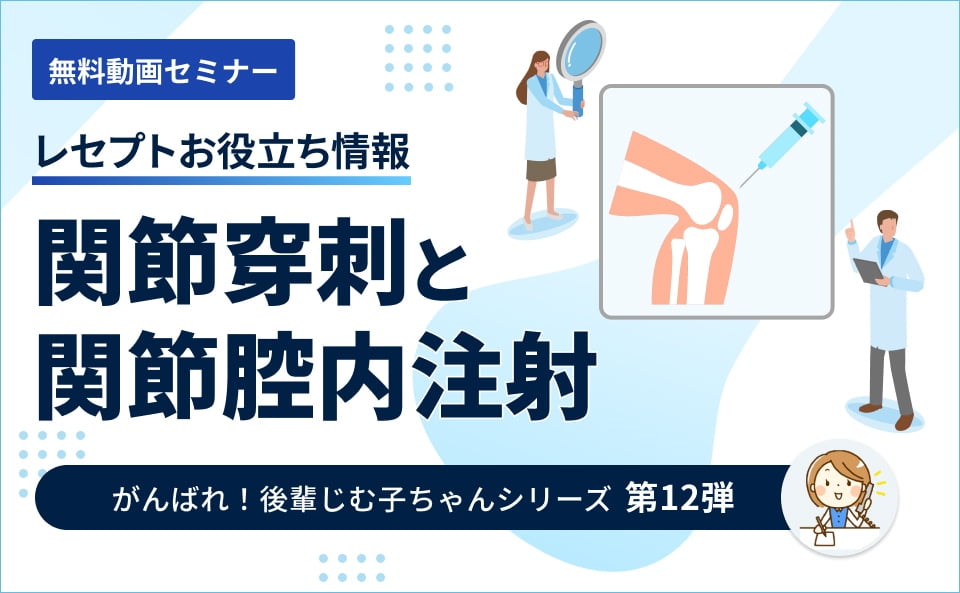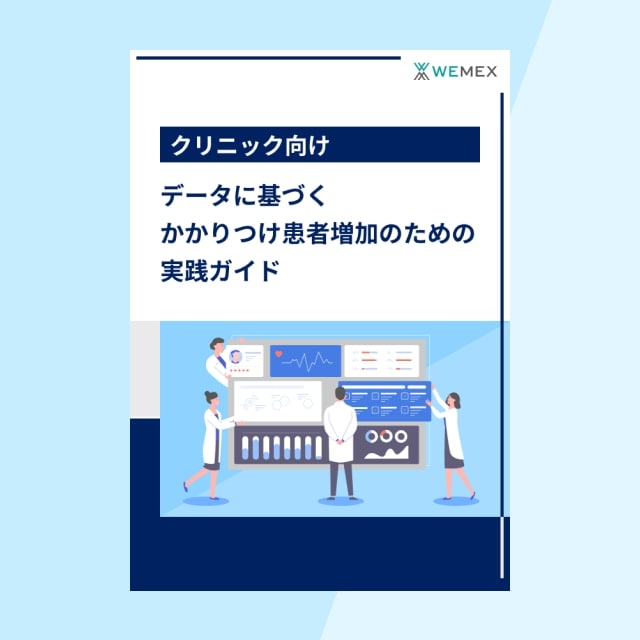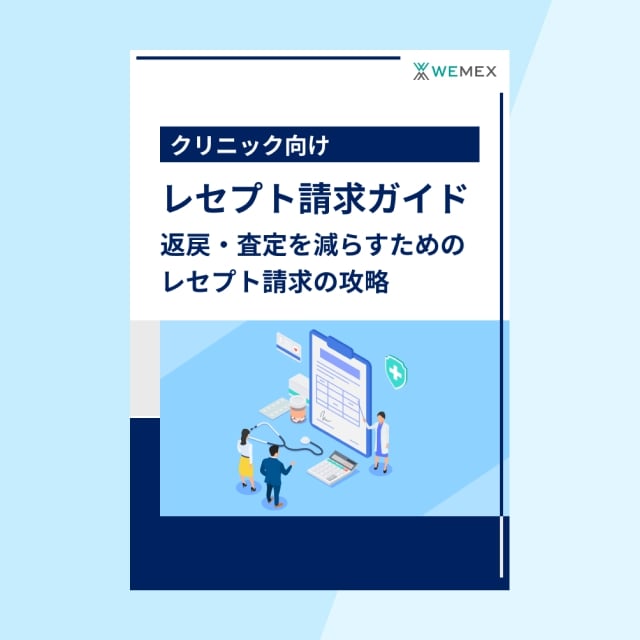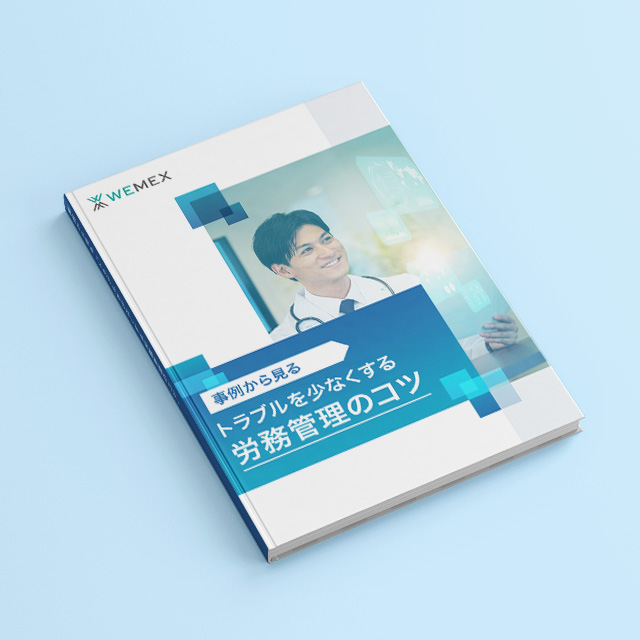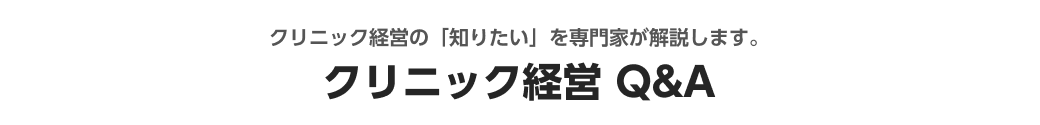
《ここがポイント!》
- 厚労省は協力医療機関の要件として往診体制を常時確保する必要はなく外来診療可能な体制で足りること、入所者専用病床の確保も不要で一般的な在宅療養者受け入れ体制があればよいとしている。
- 一方、在宅療養支援病院・診療所や地域包括ケア病棟を有する病院には、施設からの求めに応じて協力医療機関となるよう努める義務が課されている。
- 介護保険施設等が協力医療機関を定めることは、27年4月1日から義務化されるが、厚労省は「期限を待たず、可能な限り速やかに連携体制を構築することが望ましい」としている。
-
-
協力医療機関はどのような診療体制を確保すればよいのですか?
介護保険施設等の協力医療機関が確保すべき診療体制について、あらためて明確化されたと聞きました。どのような内容なのか教えてください。
-
往診が常時実施できる体制や、連携する介護保険施設等の入所者専用の病床までを確保する必要はありません。
2024年度介護報酬改定では、次の3つの要件を満たす協力医療機関を定めることが、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院などに対し、3年間の猶予期間を設けて義務付けられました。
①入所者が急変した場合などに、医師や看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること②介護施設から診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること③入所者が急変し、入院が必要と認められた場合に、原則として入院を受け入れる体制を確保していること(病院に限る)
このうち、①と②の要件について、厚生労働省は以下の点を明確にしています。①:常時外来も含めて診療が可能な体制を求めており、必ずしも往診体制を常時確保する必要はない②:入所者専用の病床を確保する必要はなく、地域で在宅療養を行う人を受け入れる一般的な体制が整っていればよい
介護保険施設等が協力医療機関を定めることは、27年4月1日から義務化されますが、厚労省は「期限を待たず、可能な限り速やかに連携体制を構築することが望ましい」としています。
一方、24年度の診療報酬改定では、在宅療養支援病院・在宅療養支援診療所・地域包括ケア病棟を有する病院に対し、介護保険施設等からの求めに応じて協力医療機関となるよう努める義務が課されました。
要件を満たす協力医療機関を選定できていない介護保険施設等のなかには、「どこに相談すればよいかわからない」といった情報収集段階での課題がみられることも、厚労省の調査で明らかになっています。医療機関側からも、自施設の診療体制などについて積極的に情報提供を行うことが望まれます。
-
協力医療機関はどのような診療体制を確保すればよいのですか?
※現場の先生方から実際にあった質問に対し、日本経営コンサルタントをはじめとした医院経営の有識者が回答しています。
質問の内容については、先生ご個人の特定を避けるため、ニュース提供元の日本経営社が一部改変した部分がございます。予めご了承ください。